言葉や文化の壁を越え共に学ぶ 言語教育だけではない多様性の教育
日本語指導が必要な児童生徒が増えている中、日本人の子どもを主眼に据える一般的な教育と外国人児童生徒に対する特別な教育という分断を見直すことが問われている。言葉も文化も多様な子どもたちが共に学ぶ「多様性の教育」の在り方を、広島大学准教授の南浦涼介氏に聞いた。
“専門家にお任せ”からの脱却
カリキュラムの問題で捉える
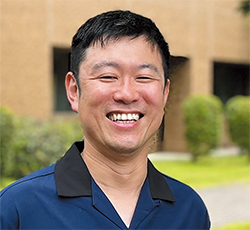
南浦 涼介
広島大学大学院 人間社会科学研究科 准教授
博士(教育学)。滋賀大学教育学部卒業後、タイの大学で日本語教師を務める。帰国後、滋賀県内の小中学校で外国人児童生徒の日本語指導などを経て、2010年、山口大学教育学部の講師に。東京学芸大学教育学部准教授を経て2023年4月から現職。教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と外国人児童生徒教育学という「特別な教育」の両方を研究。「一般/特別」の境界線自体を互いにゆさぶりあい、混ぜあわせ、色々な教師が教え、ことばと文化を多様にもつ子どもたちが共に学ぶ、まだ見ぬ「多様性の教育学のカタチ」づくりを目指している。近著に『人と社会をつなぐ評価―孤立化と分断を超えて』(共著、東信堂)がある。
── 外国人児童生徒等への教育課題が顕在化するなか、学校教育にはどういった視点が必要ですか。
南浦 最初に、外国人児童生徒や外国につながる子どもと、日本語指導が必要な子どもは、必ずしも=(イコール)ではないことを理解することが必要です。
外国につながる子ども=日本語指導が必要な子ども=「日本語指導者をどう配置するか論」になってしまうと、何か救世主的に専門家が現れれば課題が解決されるといった期待感で物事が動いてしまいます。
一方、学校で日本語指導に関わる日本語教員のほとんどは短期雇用です。年度契約のなかで来年、再来年を見据えた指導はできませんし、学校内でも一時的、周辺的な存在として捉えられがちです。
(※全文:2721文字 画像:あり)
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

