協同的な場で形作る論理的な思考 リテラシー教育の最前線
金融や情報、メディア等々、社会が複雑化・多様化するなか、学校現場では様々なリテラシーの育成が求められている。リテラシー教育を専門とする横浜国立大学准教授の石田喜美氏に、学校でリテラシー教育を実践する上での視点や、現在研究中のゲームリテラシーなどについて話を聞いた。
ともに生きていくための
「論理的」感覚を身につける
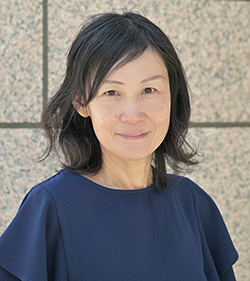
石田 喜美
横浜国立大学 教育学部 准教授
筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科修了。博士(教育学)。専門は読書教育、リテラシー教育。公益財団法人東京都歴史文化財団東京文化発信プロジェクト室主事、常磐大学人間科学部専任講師を経て、2015年4月から現職。共著に『集団で言葉を学ぶ/集団の言葉を学ぶ』(編著、ひつじ書房)がある。
── 現在、さまざまな「〇〇リテラシー」が提唱されています。そもそも「リテラシー」とはどのような概念なのでしょうか。
石田 英和辞典で「literacy」と引いてみると、たいてい、「読み書き能力」「教養」という2つの意味が書かれていますよね。「リテラシー」を考えるときにはここから出発する必要があると思います。
つまり、「読み書き能力」と「教養」とが一体化したものとして捉えるということです。例えば、「メディアリテラシー」。これは、メディアがいかに機能し、いかに制作されているかについての知識を持つこと(教養)と、メディアを読み解くこと(読み書き能力)とを不可分なものとしてみなす言葉と考えられます。
(※全文:2399文字 画像:あり)
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

