知識を身につけるだけでは不十分 学校における金融教育の難しさ
スマホ一つで決済から投資、資産運用までできる時代。お金に関する正しい理解や判断力(金融リテラシー)を養う金融教育の必要性が高まっている。学校現場で必要な金融教育とは何か。効果的な金融教育の在り方や金融教育の難しさなど、関西大学教授の本西泰三氏に話を聞いた。
金融行動の合理的な選択には
知識プラス冷静な行動が必要
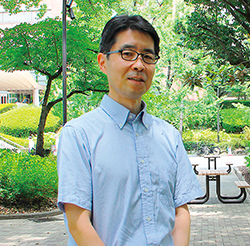
本西 泰三
関西大学 経済学部 教授
博士(経済学)東京大学。主な研究分野は金融行動、金融教育など。2007年より現職。関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構機構長(2017年~2023年)。学術誌International Journal of Economic Policy Studies編集長。大阪府労働委員会公益委員。千里山政策ディベート大会主宰。
── 2021年にRISS(関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構)の研究者と共同で発表した論文『Is Financial Literacy Dangerous?(金融リテラシーは危険なのか?)』で、“高い金融リテラシーが慎重さを欠く行動を誘発する場合がある”ことを指摘しています。
本西 この研究では、一般の方を対象にアンケートを実施し、金融知識が金融行動に与える影響を分析しました。その結果、高い金融リテラシーを持つ人が、慎重ではない行動をとる場面があることが分かりました。
ここで言う金融リテラシーとは、金利はどう計算するか、インフレがどんな効果を持つかといった、いわゆる経済学の基礎知識を指します。この金融リテラシーが高いと慎重さを欠く行動を誘発する場合があることが分かりました。
── どういう要素を背景に、そうした傾向が見られるのでしょうか。
(※全文:2519文字 画像:あり)
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

