管理社会化に立ち向かう学びへ 〜川喜田二郎・移動大学の試みから考える2
川喜田二郎は、情報は機械的に処理するだけでなく創造や生産も重要であると考え、多様な人々が共同生活を送りながら課題解決に取り組む移動大学を実践した。人と人との交わりが生む主体性や創造性は人間らしさや他者との連帯、組織活性化のカギともなる。
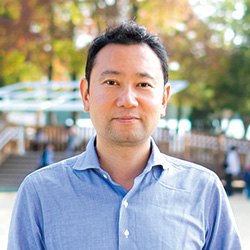
松村 圭一郎
岡山大学文学部准教授。
専門は文化人類学。所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社、第30回澁澤賞、第37回発展途上国研究奨励賞受賞)、『基本の30冊 文化人類学』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)、『これからの大学』(春秋社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)など、共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)がある。
1969年から「移動大学」をはじめた川喜田二郎は、当時から高度情報化社会の「危険性」に言及していた(『川喜田二郎著作集第8巻 移動大学の実験』)。人間は知・情・意がそろった存在にもかかわらず、現代は「知」だけが異常に突出している。だから人びとは事実よりも加工・貯蔵された間接情報に振りまわされ、扇動されやすくなる、と。インターネットで世界中の情報が手に入る時代になり、川喜田の指摘は、ますますその切実さを増している。
川喜田は、情報のやりとりには、定量的な機械的処理だけではなく、…
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

