堺屋太一 日本の近未来社会を予測し続けた「希有な実践派社会構想家」
社会構想大学院大学 社会構想研究科では、社会のグランドデザインを描き、実装できる人材を養成している。本連載では12人の社会構想家の実践から、「グランドデザイン」について解説。本稿では、日本の近未来社会を構想し、政策提言し続けた堺屋太一氏を取り上げる。
2019年に逝去された堺屋太一氏との出会いは、2017年、筆者が大阪府市副首都推進局で「副首都ビジョン」を策定していた時である。当時、大阪府市特別顧問の氏と面談を重ねるたび、徹底した調査とデータ分析に基づく構想力と鋭い洞察力に深く感銘を受けた。
また、当時、2025年大阪・関西万博の誘致活動が始まっており、氏は自身がプロデュースした1970年大阪万博の跡地利用に触れ、過去から未来へレガシーが継承されることを熱く語っていた。万博の意義を歴史・経済・文化の観点から説くその姿は、まさに万博の“生き字引”であり、同時に、「副首都・大阪」の発展への氏の強い期待を感じた。本稿では、氏の主な著作を通して、氏の社会構想(家)の特質と示された構想を紹介したい。
「空想と調査」「予測小説と造語」
を原動力とした社会構想家
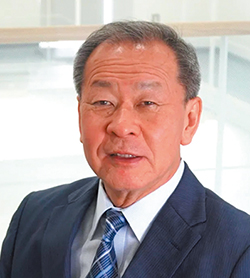
西田 淳一
社会構想大学院大学 社会構想研究科 教授
専門分野:地方自治制度/地方分権/統治構造
担当科目:総合政策概論
1979年中央大学法学部を卒業し、三井物産株式会社に入社。2012年7月同社を早期退職、公募にて同年8月大阪市西淀川区長に転身、区政・市政改革を推進。2016年大阪府・市副首都推進局企画担当部長として「副首都ビジョン」を策定。2017年4月大阪府商工労働部長に就任(2020年3月退任)。2022年3月京都大学大学院公共政策専攻専門職修士課程を修了。2021年4月~2024年3月まで大阪経済大学経済学部客員教授(非常勤)、2024年4月より社会構想大学院大学 社会構想研究科 教授。
自伝『戦後70年七色の日本』(2015年)で、氏は「少年時代から空想を拡げることと調査を深めることが好きだった」と述懐している。この空想し調査するという習慣(第一の色)が生涯に亘り氏の思考の基盤となっている。建築家を目指した浪人時代から、官僚、エコノミスト、作家、歴史家、任用政治家(経済企画庁長官・複数の担当大臣)という異色の経歴も、この習慣から生まれたものと理解できる。
また、「学問とは現象を調べ、原因を探り、共通の原理を発見すること」という氏の言葉は、複雑な社会の背後にある現象や要因を探求する氏の姿勢を表している。いわゆる「グランド・セオリー」の構築に通じるものであった。
通産官僚時代(1960~1978年)に覆面作家として発表した『油断』(1971年)や『団塊の世代』(1976年)は、「予測小説」という新たなジャンルを確立し、堺屋太一の名を世に知らしめた代表作である。時代背景や社会・経済情勢を緻密に調査・分析・シミュレーションし、官僚経験で身につけた「実践知」を融合させ小説の形で社会に訴えた。『団塊の世代』では、戦後日本のベビーブームに生まれた約800万人の人口集団が社会を動かす原動力となることを予測した。
訴えたい社会の現状や近未来を、登場人物の人生や葛藤を通して「予測小説」(物語)として描くことで、一般読者にも複雑な社会の構造的変化を分かりやすく示し、近年注目される「ナラティブ」の手法を半世紀近く前に先取りしていた。
氏の特筆すべき才能の一つに、時代や事象の本質を的確に捉えた「造語」がある。「水平分業」論初め、「戦後石油文明」「団塊の世代」「職縁社会」「知価社会」「楽しい日本」など、氏が生み出した多くの造語は、人々の関心を引きつけ、社会的な議論を喚起する力を持っていた。「巨人、大鵬、卵焼き」も1960年代の高度成長社会を反映し、大流行した氏の造語である。新たな概念をキャッチーな言葉で表現することは、氏の構想や提言を社会に浸透させる上で有効なツールとなり、共通言語としても機能した。
『知価革命』『第三の敗戦』で描く
「知価社会」と「統治構造改革」

堺屋太一氏の研究室(大阪市北区天満)。
『知価革命』(1985年)は、社会の価値観が「物価」から「知価」へと移行する変革を描き、大きな反響を呼んだ。氏は、工業社会の価値基盤であった「物価」(物材や資本)から、情報、知識、ノウハウ、知恵といった「知価」へと移行する「知価社会」の到来を予測した。
この変革が経済システムの変容に留まらず、社会全体の仕組みや個人の生き方にも影響を及ぼすことを、インターネットが普及する前の1980年代に示した。同時に、「知価社会」が個人や企業にもたらす「知価格差の拡大」や、AI・ロボットによる労働代替に伴う「雇用の不安定化」といった潜在的課題も鋭く指摘し、今日のデジタル社会が抱える課題を予測していた。
2011年の東日本大震災を契機に出版された『第三の敗戦』(2011年)は、日本の近代史における大きな転換点を三つの「敗戦」として捉え直した。氏は「敗戦」を「一つの国の倫理観と社会体制と統治構造が全く変わってしまう現象」と定義している。
•第一の敗戦:幕末→鎖国から開国・体制転換と「強い国」作り
•第二の敗戦:太平洋戦争→規格大量生産型工業社会の確立
•第三の敗戦:東日本大震災→官僚主導の戦後レジームからの脱却
氏は第三の敗戦からの復興は、決して「古い日本」(官僚主導・業界協調の戦後成長モデル)に戻してはならないと主張し、「知価社会」への本格的な移行、「地域主権型道州制」(東京一極集中・中央集権体制を打破する「統治構造改革」)、「官僚身分制度の廃止」といった改革を包括的に提言している。一方で、現実の日本社会が未だ「古い日本」を乗り越えられずにいる状況を厳しく批判している。
「大阪都構想」に託した
「統治構造改革」への執念
晩年の氏が最も注力したのは、2007年、橋下徹(元大阪府知事・市長)との出会いを機に始まる「大阪都構想」を起点とする「統治構造改革」であった。1970年大阪万博を成功させ大阪の潜在力を熟知していた氏は、この改革を「第三の敗戦」を乗り越える「維新」と位置づけていた。『体制維新』(2011年)や『「維新」する覚悟』(2013年)といった著作は、氏の改革への信念の強さを物語る。
特に、氏の最後の予測小説『団塊の後~三度目の日本~』(2019年)は、2026年の日本を舞台に、「大阪都構想」が既に実現し、「二都二道八州の日本」への改革に向け首相が国会で熱く所信表明する場面やTV討論で訴える状況が臨場感をもって描かれている。まさに氏の信念と執念の結晶作である。
実際には、「大阪都構想」は住民投票で二度とも僅差で否決され、統治構造改革(道州制)は、2010年代半ばから国での議論が途絶え、本丸である制度改革には踏み込まない「地方創生」に関する諸策だけが進んでいる現状にある。
氏が亡くなり、来年で7年が経とうとしている。「現実との乖離」や「実行性の問題」といった氏への批評もあるが、異色(七色)のキャリアを武器に「希有な実践派社会構想家」として、日本の近未来社会を構想し政策提言し続けた功績と社会に与えたインパクトは大きい。
今日、「知価革命」は、生成AIの進化によって「古い日本」に変化をもたらし始めている。一方で「官僚主導の戦後レジームからの脱却」は、今も日本社会は「古い日本」という蟻地獄の中でもがき続けている。氏が提唱した「第三の敗戦」からの「維新」、すなわち動き始めた「知価革命(社会)」を支える土台となる「統治構造改革」が今まさに国に求められている。実現を待つ氏の姿が浮かぶようで筆者も改めてその認識を深めている。

