大阪大学の坂口志文特任教授がノーベル生理学・医学賞を受賞 免疫の「ブレーキ役」発見
スウェーデンのカロリンスカ研究所のノーベル会議は2025年10月6日、同年のノーベル生理学・医学賞を、大阪大学免疫学フロンティア研究センターの坂口志文(さかぐち しもん)特任教授、システム生物学研究所(米国シアトル)のメアリー・E・ブランコウ博士、ソノマ・バイオセラピューティクス(米国サンフランシスコ)のフレッド・ラムズデル博士の3氏に授与すると発表した。
坂口特任教授は1951年1月19日生まれ、愛知県出身。1976年に京都大学医学部を卒業後、米国のジョンズホプキンス大学やスタンフォード大学などで研究を重ね、1999年から京都大学再生医科学研究所教授、2011年から大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授を務め、2017年には大阪大学栄誉教授の称号を授与されている。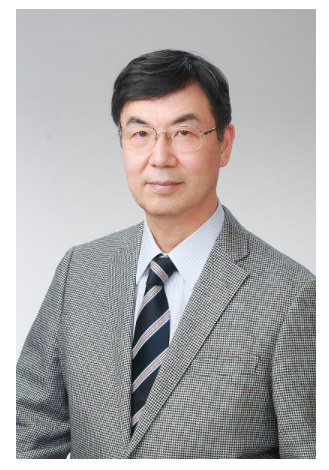
大阪大学のホームページより
今回の受賞は、体を守る免疫システムが暴走しないよう制御する仕組みの発見が評価されたもの。坂口氏は1979年から研究を開始し、1995年に免疫の働きを抑える「制御性T細胞」という新しい細胞の存在世界で初めて証明した。これは免疫システムに抑制機能を持つ細胞が存在することを世界で初めて証明した歴史的な発見だった。
その後、ブランコウ博士とラムズデル博士が2001年に重要な遺伝子を特定し、2003年に坂口氏がこの遺伝子と制御性T細胞の関係を解明したことで、発見の意義が確立された。
受賞決定を受け、坂口氏は記者会見で「大変光栄に思う。ともに研究を進めてきた多くの仲間、学生、共同研究者の皆さまに心より感謝申し上げる」と喜びを語った。さらに、「この成果が、自己免疫疾患やアレルギー、がんなどの新しい治療法につながることを心から願っています」と述べ、今後の医療への応用に期待を示した。
坂口氏は「今後も若い研究者が自由な発想で基礎研究に挑戦できる環境づくりに力を尽くしたい」と、次世代の研究者育成への意欲も語った。

