留学生獲得の国際競争が進む現在、大学は留学生目線での獲得戦略を
急速に少子化が進む中、国内の大学では、外国人留学生を含む多様な学生の受け入れ促進が求められている。その一方で、外国人留学生の受け入れに関しては、様々な壁も存在する。国際教育に詳しい関西国際大学教授の芦沢真五氏に、日本における課題や必要な施策について話を伺った。
かつては留学生の供給国だった
国も留学生獲得で競争相手に
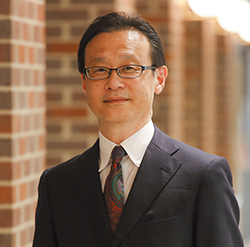
芦沢 真五
関西国際大学
副学長・国際コミュニケーション学部 教授
ハーバード大学教育大学院卒(国際教育専攻ED.M)、慶應義塾大学、大阪大学、明治大学、東洋大学を経て、2022年4月より現職。高等教育機関の国際化にかかわる比較研究が専門。主な論文に「転換期の教育交流と国際教育の将来像:コロナ禍における教育交流のパラダイムシフト」(2020年)"Student and Skilled Labour Mobility in the Asia Pacific Region, Reflecting the Emerging Fourth Industrial Revolution" (Palgrave Macmillan, 2023)など。一般社団法人国際教育研究コンソーシアム代表理事。
中央教育審議会が昨年公表した答申案※1の要旨では、2021年に62.7万人だった大学進学者数が2040年には46万人に減少すると推計。答申案は、今後の高等教育政策の方向性と具体的な方策の1つに、外国人留学生を含む多様な学生の受け入れ促進を挙げている。一方で、世界の大学における留学生獲得に向けた国際競争は近年、激化している。
(※全文:2642文字 画像:あり)
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

