行動分析学×デジタルで学校改革 インクルーシブな先進教育とは
長野県の廃校が画期的な小学校に生まれ変わる。行動分析学に基づくインクルーシブ教育を実践する学びの場「さやか星小学校」(2024年4月開校予定)だ。創立者で理事長の奥田健次氏は、国際的に活躍する臨床心理士。今回、開校を目指している経緯や学校づくりのコンセプトなどについて聞いた。
理想の学校をつくるという
夢に突き動かされて
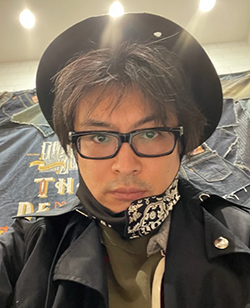
奥田 健次
学校法人西軽井沢学園 創立者・理事長
応用行動分析学、行動療法を専門とする心理臨床家。発達につまずきのある子とその家族の支援のため、国内外からの支援要請に応える国際的セラピスト。あらゆる行動上の問題を解決に導くオーダーメイド化されたプログラムとそのアウトカムが注目され、その手腕はしばしばメディア等で紹介されている。日本初の行動分析学に基づく幼稚園を創立(学校法人西軽井沢学園サムエル幼稚園)。日本子ども健康科学会理事、日本緘黙研究会常任理事(副会長)。一般社団法人日本行動分析学会理事などを歴任。専門行動療法士、臨床心理士。
── 新しい学校づくりを目指されたきっかけをお聞かせください。
奥田 大学院生の頃から、恩師(鳥取大学教授 井上雅彦氏)と共に理想の学校をつくるという夢を語り合っていました。公立学校の画一的な教育に疑問を感じていたからです。資産家でもない一介の大学教員の身では本当にただの夢物語でしたが、小さな幼稚園なら作れるのではないかという考えに至りました。
(※全文:4273文字 画像:あり)
全文を読むには有料プランへのご登録が必要です。
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

