『科学で未来を創造する大学へ─Team東工大、2,374日の挑戦』

『科学で未来を創造する大学へ
─Team東工大、2,374日の挑戦』
益 一哉 編著/384頁/1600円+税/ダイヤモンド社
東京工業大学は2024年10月、東京医科歯科大学と統合し、東京科学大学に生まれ変わった。研究力や国際性などが国内最高水準とされる「指定国立大学法人」同士の統合は日本初とあって話題を呼んでいる。本書には、東工大の最後の学長として、2018年から6年半、2,374日にわたって同大の改革を牽引した益一哉氏を中心に教職員が協働し、「Team東工大」として世界最高峰の理工系大学を目指した挑戦の軌跡が綴られている。
東工大の前身は、明治初期の1881年に設立された東京職工学校。以来140年にわたり、日本の工業教育の礎を築き、時代の要請に応じて進化を続けてきた。いよいよ変化のスピードが加速してきた近年、同大で行われてきた教育面における改革の中心となったのが「学院制」だ。2016年4月、同大は日本の大学で初めて学部と大学院を統一した「学院」を創設した。従来は3学部23学科、6研究科45専攻にも細分化されていた組織を6学院19系にまでスリム化したという。これにより、入学時点で専攻を絞りきれていなくても、より広い視野で学びをスタートできる。また、学部と大学院とのカリキュラムに一層の連続性を持たせることで、実質的に6年間の一貫教育を行えるようになったという。
研究面においても同様に、2016年に科学技術創成研究院を設立するなどの改革を進めてきた。複数の研究所を1つの大きな組織にまとめ、分野間の垣根を低くすることで、新しいテーマに積極的に取り組める体制が整ったという。
こうした改革による効果を最大化するため、益氏が学長に就任した際、大学法人全体の組織構造の見直しが必要とされた。そこで生まれた新しい組織が「アドバンスメントオフィス」だ。「世界最高水準の知と人材を人類社会に還元するため、学長が主導する多様な社会との連携活動を、戦略的組織的に推進し、その高度化を図る」ことを目指してのことだ。大学全体の戦略と密接に連携しながら活動でき、組織横断的な取り組みや迅速な意思決定につながったという。
こうした改革を重ねてきたからこそ、東京医科歯科大学とも単なる連携法人ではなく、法人統合・大学統合という大胆な変革に乗り出せたのだろう。新たに誕生した東京科学大学は、「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」をミッション に掲げ、理工学と医歯学との「医工連携」で、新しい研究分野を開拓するとしている。この統合が社会にどのような貢献がもたらすのか、新たな航海を始めた同大の行く末に注目したい。
新刊一覧
●教育学
教育方法学辞典
日本教育方法学会 編/368頁/5800円+税/学文社
●学校教育一般
もう困らない! 教育・保育給付制度の手引
~配置基準から加算の内容まで~
網干 達也、本岡 伸朗 著/200頁/2700円+税/ぎょうせい
●学級経営
授業力を高める「受けの技術」
山中 伸之 著、野口 芳宏 監修/152頁/1800円+税/さくら社
●高等教育
立命館がすごい
西山 昭彦 著/408頁/1500円+税/PHP研究所
「キャリアデザイン」って、どういうこと?
過去は変えられる、正解は自分の中に
武石 恵美子 著/72頁/630円+税/岩波書店
●ICT
授業・校務がより速くクリエイティブに!
さる先生の実践Canva
坂本 良晶 編著/114頁/2000円+税/学陽書房
●幼児教育
3. 4. 5歳児保育 計画通りにいかない!
ジグザグ保育がつくる子ども主体の学び
今川 公平 著、佐川 早季子、山本 一成 編著/160頁/1700円+税/Gakken
0〜5歳児保育の写真・動画から学ぶ
保育を見ること、語り合うこと
西 隆太朗、伊藤 美保子 著/112頁/1900円+税/小学館
●特別支援教育
たった3つのMBA戦略を使ったら
発達障害の息子が麻布中学に合格した話
赤平 大 著/256頁/ 1600円+税/飛鳥新社
教師、支援者、親のための
境界知能の人の特性と支援がわかる本
梅永雄二 著/128頁/1800円+税/中央法規出版
●人材育成・マネジメント
組織変革の教科書
リーダーが知っておきたい人と心の動かし方
古野 庸一、今城 志保、武藤 久美子 著/388頁/2800円+税/東洋経済新報社
ユニクロの仕組み化
宇佐美 潤祐 著/288頁/1700円+税/SBクリエイティブ
組織をゾーンに入れる会議の魔法
伊賀 聡 著/400頁/1800円+税/日経BP
発達障害グレーゾーンの部下たち
舟木 彩乃 著/232頁/950円+税/SBクリエイティブ
リーダーのための
コーチングがイチからわかる本
部下を持ったら身につけたい!
あべき 光司 著/264頁/1700円+税/すばる舎
●その他
東大卒収納コンサルタントが教える
子どもが自然と集中する
学習空間のつくり方
米田 まりな 著/192頁/1500円+税/日本能率協会マネジメントセンター
そうなんだ! 子どもの権利
手丸かのこ イラスト、渡辺大輔 監修/160頁/1500円+税/子どもの未来社
AIにはない「思考力」の身につけ方
ことばの学びはなぜ大切なのか?
今井 むつみ 著/128頁/1200円+税/筑摩書房
注目の一冊
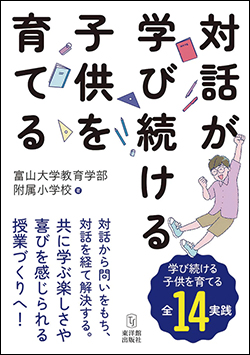
『対話が学び続ける子供を育てる』
富山大学教育部附属小学校 編著/176頁/2400円+税/東洋館出版社
「学び続ける子供を育てる研究」に取り組み続ける富山大学教育学部附属小学校。着目するのは、授業づくりにおける「対話」だ。
ここで言う対話とは「子供が必要感をもって相手を求め、互いに受け入れ、考えを吟味し合うこと」。子供自身が必要と感じるからこそ、対話を楽しみ、学びを深めることができるのだろう。
対話の前提となるコミュニケーションの力を傾聴力、理解力、発信力、共感力の4つで整理した後、各教科における授業実践例を詳しく紹介。明日からの授業にもすぐ役立ちそうだ。

