『政治哲学講義─悪さ加減をどう選ぶか』

『政治哲学講義─悪さ加減を
どう選ぶか』
松元 雅和 著/264頁/900円+税/中央公論新社
現代の政治をめぐる多くの問題は、何が「正しい」かではなく、どの「悪」を相対的に選ぶべきかという判断にかかっている。本書は、まさにそうした「悪さ加減の選択」をめぐる政治哲学の試みだ。政治哲学とは、制度や政策のあり方を「べき論」の観点から分析し、再構成する学問分野である。
2010年代以降、マイケル・サンデル氏の正義論が広く紹介されるようになった。「暴走するトロッコの進路を切り替えることで、5人の命を救う代わりに1人を犠牲にすることは許されるのか」という形で提示される「トロッコ問題」で知られる。まさに「悪さ加減の選択」といえるが、こうした思考実験には、安直な二者択一に単純化してしまう危うさもある。実際には、「誰が」「どんな立場で」「どんな関係性において」その行為を行うのかといった文脈的情報抜きには判断できない場面が多い。本書もその点を正面から捉え、より現実に即した「悪さ加減の選択」を論じるために、小説や劇作品などの物語的素材を積極的に取り上げている。
各章で取り上げられる題材は多様だ。ギリシア悲劇「アンティゴネー」、メルヴィルの遺作『ビリー・バッド』、さらには現代ドイツ作家フェルディナント・フォン・シーラッハの劇作品『テロ』に至るまで幅広い。これらの作品を通じて、読者は特定の登場人物の立場に身を置き、現実的なジレンマの中で「どの悪を選ぶか」を実感を伴って考えることになる。
例えば第4章で扱われる『テロ』は、ドイツ空軍の少佐が、テロリストにハイジャックされた航空機を撃墜し、164名を犠牲にしてサッカースタジアムにひしめく7万人の観衆を守った末に裁かれるという架空の裁判劇だ。ここでは、誰かを救うために、別の誰かを犠牲にしてよいのか、数の多いほうを救うことが善なのかという問いを突きつけられる。結果の合理性だけでなく、倫理の根本を揺さぶる問題だ。
「悪さ加減の選択」は政治家や専門家に限られたものではなく、民主主義社会において主権者である私たち一人ひとりの判断につきまとう問題だと著者は言う。選挙で投じる一票、あるいは日常の政治的態度もまた、制度や政策の「悪さ加減」をどう評価し、何を許容するかという選択に他ならない。理想主義でもニヒリズムでもなく、現実に踏みとどまりながら倫理的判断を重ねる姿勢が求められる。抽象と具体、理性と感情を往還しながら、読者自身に様々な「選択」を迫ってくる本書は、新書というコンパクトな体裁ながら、非常に歯ごたえがある。ぜひ、じっくりと読み解きたい。
新刊一覧
●学校教育一般
指導と評価を一体化する「授業研究の創り方」
知識構成型ジグソー法に基づく仮説検証型授業研究のススメ
飯窪 真也、齊藤 萌木、白水 始、一般社団法人教育環境デザイン研究所 CoREFプロジェクト推進部門 著/256頁/
2100円+税/東洋館出版社
教師のポテンシャルが開花する授業の
「見方・伝え方」
佐野 浩志 著/208頁/
2000円+税/東洋館出版社
●学級経営
チーム担任制
中西 茂、高橋 幸夫、西門 隆博、永井 初男、
苫野 一徳 著/178頁/
1800円+税/さくら社
●特別支援教育
「残念な授業」を「いいね」に変える
子どもの学び方に合わせた
インクルーシブな授業づくり
小野寺 基史 著/144頁/
2000円+税/明治図書出版
発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全
本田 秀夫 著/256頁/
1600円+税/フォレスト出版
「援助を求める力」を大切にする支援
子ども・保護者・教師の援助要請
阿部 利彦 著/188頁/
2000円+税/中央法規出版
不登校を克服する
海野 和夫 著/288頁/
1100円+税/文藝春秋
不登校のあの子に起きていること
高坂 康雅 著/224頁/
900円+税/筑摩書房
風穴をあける学校
不登校生が通う特例校
草潤中が切り拓く子どもたちの未来
佐藤 明彦 著/192頁/
1800円+税/時事通信出版局
●ICT
教師のためのAI教育入門
福原 将之 著/168頁/
1860円+税/明治図書出版
●人材育成・マネジメント
図解 人材マネジメント入門
人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための
「理論と実践」100のツボ
坪谷 邦生 著/272頁/
2600円+税/ディスカヴァー・トゥエンティワン
個性を活かす経営と人事
認知・非認知の経営学
鈴木 智之 著/264頁/
2500円+税/日本能率協会マネジメントセンター
両利きのプロジェクトマネジメント
結果を出しながらメンバーが主体性を取り戻す技術
米山 知宏 著/304頁/
2200円+税/翔泳社
トリニティ組織
人が幸せになり、生産性が上がる「三角形の法則」
矢野 和男 著、平岡 さつき 協力/256頁/
1800円+税/草思社
世界標準の1on1
スティーヴン・G・ロゲルバーグ 著、
本多 明生 訳/296頁/
2100円+税/ディスカヴァー・トゥエンティワン
●その他
教育ビジネス
子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養
宮田 純也 著/272頁/
1680円+税/クロスメディア・パブリッシング
とびこえる教室
フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」
星野 俊樹 著/262頁/
1700円+税/時事通信出版局
「主体性」はなぜ伝わらないのか
武藤 浩子 著/208頁/
900円+税/筑摩書房
ラーゴムが描く社会:
スウェーデンの「ちょうどよい」国づくり
鈴木 賢志 著/224頁
2200円+税/新評論
注目の一冊
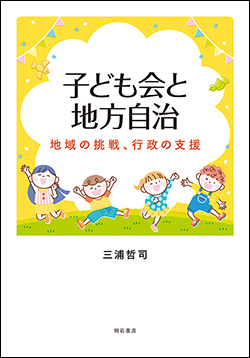
『子ども会と地方自治
地域の挑戦、行政の支援』
三浦 哲司 著/244頁/
4500円+税/明石書店
かつて盛んだった「子ども会」が存亡の危機にある。共働き世帯の増加に伴い、運営を担う人材が不足し、休止・解散を余儀なくされるケースも多い。
地方自治論を専門とする著者によれば、子ども会は「地域への最初の入り口」という大事な役割を担う。どうすれば、子ども会離れは止まるのか。その問題意識から、リスケーリングや組織改革、支援事業の再直営化など、時代状況に見合った運営と活動のあり方を理論と実践の両面から分析。子どもの教育にとっても地域活性化にとっても示唆に富む一冊だ。

